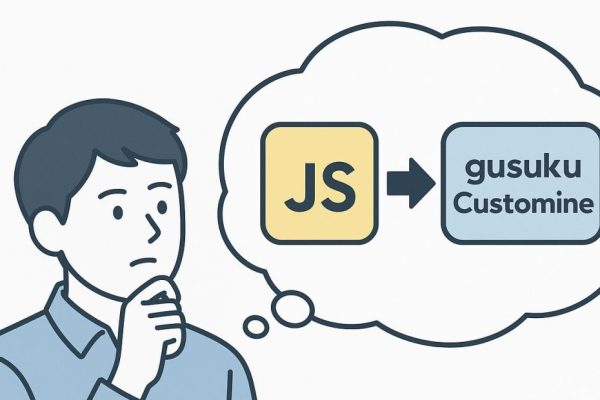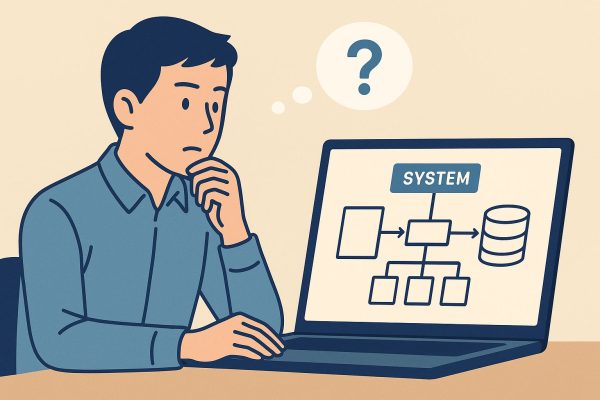公開日:
こんにちは。システム開発グループの大澤です。
システムの開発や運用を考えるとき、「保守をどう担うか」というテーマは避けて通れません。従来のシステム開発では、システムの開発も保守もすべてベンダーに依頼するのが一般的でした。自社内で開発や改修を担えるだけの人材やノウハウを持つ企業は限られており、外部に依存せざるを得なかったのです。
しかし、kintoneのようなノーコード・ローコードプラットフォームが広がったことで状況は変わりました。開発を自分たちで行うという選択肢が現実的になり、運用・保守のあり方も多様化しています。自分たちで開発したシステムはもちろん、ベンダーに依頼したシステムであっても、キミノマホロの「ハ-5 自走化に向けた引き継ぎ」のような支援メニューを活用すれば、保守を自分たちで担うことも可能になってきました。
では、kintoneを利用したシステムの保守についてはどう考えればよいのでしょうか。
自分たちで保守をする場合
メリット
- 改修スピードが速い
現場の声をすぐに反映できるのは、自作・自社保守の大きな強みです。営業担当が「この項目を追加したい」と思ったら、その日のうちに反映できることもあります。業務の変化に即応できる点は、柔軟性が求められる時代に大きなアドバンテージとなります。 - コストを抑えられる
外部に依頼しなければその分の保守費用は発生しません。小さな改善を積み重ねていくスタイルであれば、社内リソースで十分対応可能です。 - 社内にノウハウが蓄積する
使いながら改修を繰り返すことで、社内に知識が溜まり、次第に改修スピードが速くなっていきます。長期的には、自社独自の運用ノウハウという資産を持つことにつながります。
デメリット
- ノウハウが属人化しやすい
「あの人しかアプリをいじれない」といった状況は珍しくありません。担当者の異動や退職が発生すると、途端に保守が立ち行かなくなる危険があります。 - 対応が場当たり的になりがち
目の前の要望に応えることを優先すると、長期的に見るとデータ構造が複雑化し、かえってメンテナンス性が悪化します。 - 複雑なシステムには対応しにくい
外部システムとの連携や高度な自動化が必要になると、社内メンバーだけでは対応が難しくなることもあります。
うまくやるための工夫
- ドキュメント整備・ガイドライン作成
アプリの設計意図や運用ルールを記録に残すことで、属人化を防ぎます。 - チーム体制の構築
管理者を複数人置き、ナレッジを共有することで人の入れ替わりによるリスクを分散します。
ベンダーに保守を依頼する場合
メリット
- 人事異動・退職の影響を受けにくい
社内の担当者が変わっても、ベンダーが知識を持ち続けているため、システムがブラックボックス化するリスクを抑えられます。 - 専門知識に基づいた安定運用
kintoneに精通したベンダーが設計・保守を担うことで、品質の高い運用が可能になります。設計の乱れによる将来的な不具合リスクも軽減されます。 - 外部システム連携や高度な改修にも対応可能
API連携やワークフロー設計など、社内では難しい高度なシステムであっても問題なく保守できます。
デメリット
- 固定コストが発生する
保守契約や改修依頼のたびに費用がかかります。保守契約は実績ベースではなく月額固定のことが多いので、ほとんどトラブルや問い合わせがない場合でも毎月費用が発生することになります。 - 小規模な改修でも依頼が必要
「一覧画面を少し変えたい」といった小さな変更でも依頼が必要になり、改善スピードが落ちることがあります。 - 社内に知識が残りにくい
ベンダーに丸投げしてしまうと、自社にノウハウが蓄積されず、依存度が高まってしまいます。
うまくやるための工夫
- 保守契約の範囲を明確化する
定例改修、緊急対応、相談サポートなどを整理し、「どこまでがベンダー対応か」を明確にしておくことが重要です。
できるだけ費用がかからないように、定期的に保守工数の見直しを行うことも必要です。 - ハイブリッド型運用が可能なベンダーを選ぶ
頻繁な改修が必要な部分は自社で行い、基盤部分や高度な連携はベンダーに任せる、といった役割分担も効果的です。
単なる外注先ではなく、知識を社内に移転しながら支援してくれるベンダーを選ぶことで、自社の成長にもつながります。
自社にあったスタイルを見極める
「保守を自分たちで担うか、ベンダーに依頼するか」は、企業の規模や人材リソースによって最適解が異なります。
- 小回りとスピードを重視するなら自社保守
- 安定性や高度な改修対応を重視するならベンダー依頼
ですが、重要なのは“どちらか一方に決め打ちする”ことではありません。自社でできる範囲と、ベンダーに任せる範囲を見極め、適切に組み合わせることです。
その見極めができれば、kintoneは単なる「導入しただけのシステム」から、「成長し続ける基盤」へと育っていきます。
まとめ
今回は、私の経験からkintoneのシステム保守の考え方についてご紹介しました。
アールスリーでは本記事でご紹介したような、弊社で開発後にお客様に引き継ぎを行い、保守を移管するなどの柔軟な運用にも対応しています。
「まずは、どんなことができるのか話を聞いてみたい」
そんなお気軽なご相談でかまいません。ぜひ一度お問い合わせください。
キミノマホロ for kintone
アールスリーでは業務改善・システム開発を行うサービスを「キミノマホロ for kintone」として提供しています。
「キミノマホロ for kintone」は業務改善のプロセスをイロハで3つのフェーズに分け、フェーズごとに作業をメニュー化しています。
【イ】業務改善の始まり:業務改善の方向性を決める
【ロ】業務改善に必要なkintoneアプリ作成:業務改善を実現するための仕組み(kintoneアプリ)を作る
【ハ】業務改善の実行サポート:業務改善を進める
システム開発グループではkintoneに関するお悩み相談をお受けする「kintone駆け込み相談室」を随時開催しています。kintoneのシステム開発でお悩みの方がいらっしゃいましたらぜひお申し込みください!
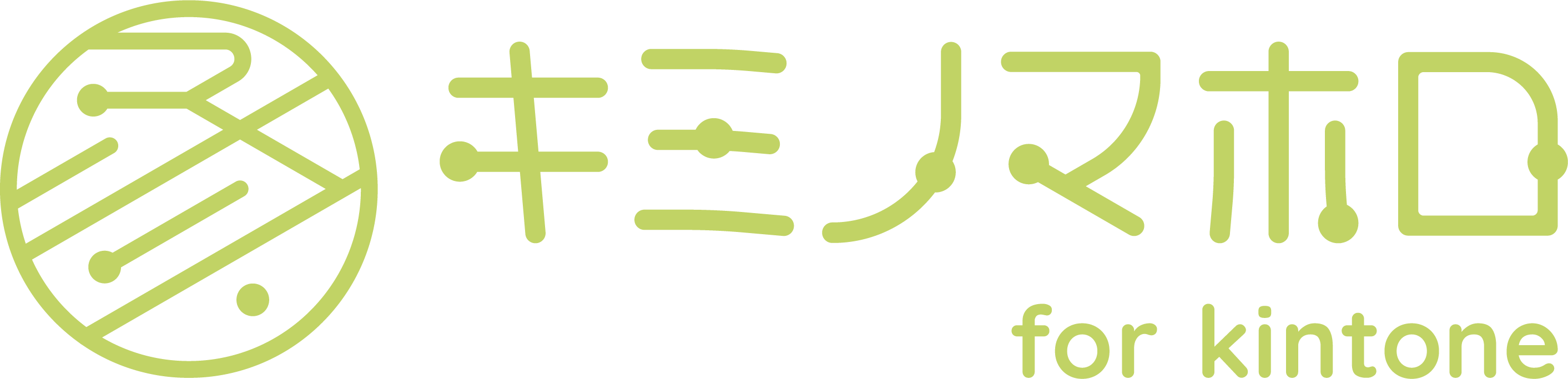
必要なものを、必要なだけ。
業務改善の新しいカタチ。
kintoneを活用した業務改善・システム開発サービス
kintoneを活用した業務改善・システム開発サービス
投稿者プロフィール
- システム開発グループ マネージャー
最新の投稿
 kintone2025年12月19日JavaScriptカスタマイズをカスタマインに移行する時に大事なこと
kintone2025年12月19日JavaScriptカスタマイズをカスタマインに移行する時に大事なこと kintone2025年11月14日kintone開発の仕様検討って何をするの?
kintone2025年11月14日kintone開発の仕様検討って何をするの? kintone2025年10月17日業務改善アシストをうまく使っていただくために必要なこと
kintone2025年10月17日業務改善アシストをうまく使っていただくために必要なこと kintone2025年9月19日kintoneシステムの保守どうしてますか?
kintone2025年9月19日kintoneシステムの保守どうしてますか?