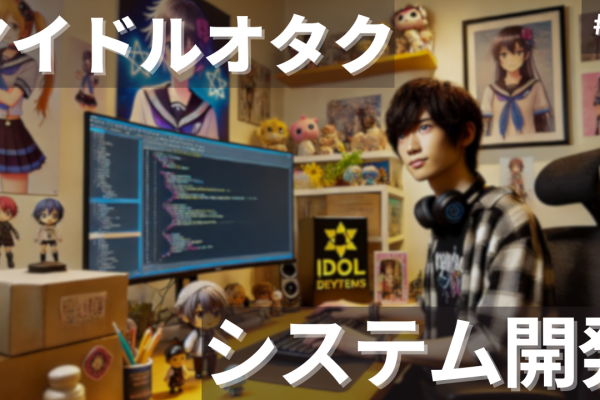公開日:
こんにちは。システム開発グループの井上(たーぼー)です。
今日は、kintoneで仕組みをリリースしたその後の3週間をどう過ごすか、私が現場で大切にしている考え方をまとめます。導入の成功は「作った日」ではなく、「使い続けられるようになった日」に決まる。だからこそ、リリース直後の“お試し運転”を設計しておくのが肝です。目的から考えるワークショップの流れ、持続可能なガバナンスの考え方とも地続きの話です。
なぜ「3週間」なのか
3週間は、現場が“慣れる/困る/言い始める”最初の波が出そろう絶妙な長さ。
- Week 1:初期の“つまずき”が露出する
- Week 2:小さな改善で体感が変わる
- Week 3:続ける/待つ/方向転換/やめるを決められる
大事なのは、観察 → 測定 → 決定のリズムをあらかじめ決めておくこと。ルールは現場を縛るためではなく、現場の自由度を持続させるための設計だと捉えています。
Week 1:まず“音を聴く”(観察)
最初の1週間は、事実を集めるに徹します。要件を詰め直すより、日常の違和感を拾うほうが効きます。
1) 10分インタビュー
- 迷子ポイント、二重入力、承認の滞留をその場でメモ
- 聞くのは「良かった瞬間/困った瞬間」「今日1つだけ直せるなら?」だけでも十分
2) 先行指標で“体温測定”
- 対象者のうち実際に使った人の割合
- 初回完了率
- 申請→承認のリードタイム
- 問い合わせ/差戻し件数(Point 1/2/3で区分)
3) 基準を全員で共有
- Point 1=業務停止級:即応(回避策→恒久策)
- Point 2=痛いけど回る:48時間以内に治し方の見立て
- Point 3=“あると嬉しい”:Week 2の候補箱へ
4) データ品質の“初動”
必須未入力や重複・整合エラーは最初の3日で手当。ここが曖昧だとWeek 2以降の判断がぶれます。
迷ったら合言葉は「このまま使い続けていいか?」。
使ってもらえなければ、良い仕組みもただの飾りです。
Week 2:“小ネタ改善”で体感を変える
2週目は、小さく速い改善で「お、使いやすい」を増やします。
1) 3分で効くネタを束ねる
- フィールド並び順
- 検索条件の保存
- 通知の時間帯・頻度
- 承認の代行設定
- ツールチップ/ガイド文言
2) 仮説 → 実験 → 計測
- 例:「通知を業務時間内に絞れば承認が早まるはず」
- 2日間試す → リードタイムの中央値で効果判定
3) 定着の壁を3つ以内に特定
- 30秒動画/スクショ1枚/ひとことガイドで塞ぐ
- 説明資料は1枚:「誰に/何が/どう便利になったか」を冒頭に
プロマネ視点のコツは期待値のコントロール。小さなリリース単位で合意形成を積み上げ、成功体験を増やします。
Week 3:三択+1会議(Go / Hold / Pivot / Stop)
3週目は、腹をくくる会を1本。ダッシュボードは難しくしない。
定着の目安(例)
- 対象者の7割が3回以上使っている
- リードタイム/差戻し率がベース比20%以上改善
- 必須未入力や重複がほぼ解消
三択+1
- Go(進める):月次改善へ。権限・監査は定例化
- Hold(保留する):2週間だけ延長し、決定的な課題を1〜2点だけ潰す(期限とKPIを明記)
- Pivot(方向転換する):対象や順番を変える(スコープ縮小、先に別部署など)
- Stop(中止する):価値<コスト、コンプラ壁で本質価値が出ない、現場プロセスと齟齬が大きい——なら潔く撤退
撤退時はロールバックとデータアーカイブを淡々と。「なぜやめたか/何を学んだか」を1枚に残すと、次の挑戦が速くなります。
「現場への浸透支援(ロ-5)」をつかうと…
この“3週間お試し運転”のWeek 1〜Week 2で投入すると、次のような変化が起きます。
- 回し方が具体化する
完成アプリをシミュレーションしながら、実運用の手順と役割分担が“絵”から“手順”になります。
→ 「誰が、いつ、どの画面で、何を入力するか」が明文化され、迷子が減ります。 - 初回完了率が上がる
利用者向けの操作説明/ミニトレーニングを挟むことで、最初の1往復を自力でやり切れる人が増えます。
→ “触って終わり”から“仕事が完了した”へ到達する人が確実に増えます。 - 詰まりどころがその場で潰れる
迷子ポイントは軽微な修正(フィールド並び替え、文言・ツールチップ追加、通知タイミング見直し等)で即日〜数日内に解消できます。
→ 「ちょっと使いにくい」が「まあ使える」へ。 - 足並みがそろう
進め方・スケジュールの計画書が用意され、チーム全体のゴール・期限・担当が一本化されます。
→ “やることリスト”が共有され、会議が意思決定に集中します。 - スモールスタートを守れる
“ここはプロに押してもらう/ここは自分たちでやる”の線引きが明確になり、小さく・早く・安全に回せます。
→ 自走と統制のバランスが崩れません。
作業範囲の目安:打合せ1〜2回/計画書の作成/質疑対応/軽微な修正対応(費用感:30万円〜)。
向いている状況:
- 使い始めの迷子が多い・初回完了率を押し上げたい
- 現場に説明する材料(資料・動画)が不足している
- “改善したい点”は見えているが、優先順位と実施計画が定まらない
まずは自分たちで回す。ハンドルが重いところだけ外部の力で軽くする。
その結果、3週目のGo/Hold/Pivot/Stopの判断が、数字と手触りで語れるようになります。
3週間のチェックリスト(貼って使ってOK)
Day 1–3
- 基準(Point 1/2/3)を決めて告知
- 初回完了率をダッシュボードで見える化
- 10分インタビューを1日3人ペースで
- 迷子ポイントを「今週直す/来週候補」に仕分け
Week 2
- 小ネタ改善を3つだけ選ぶ
- 30秒動画/スクショ/ひとことガイドを用意
- 中央値で効果判定
- 必要ならロ-5を投入(操作説明・軽微修正・計画作成)
Week 3
- 定着スコアを“3指標だけ”で評価
- Go/Hold/Pivot/Stopを会議1本で決定
- 説明資料(1枚)と「来月の改善テーマ」を掲示
- 撤退なら中止&学び1枚
まとめ:作って終わりにしない、3週間の“型”
- Week 1:観察とベースライン
- Week 2:小ネタ改善で体感を変える
- Week 3:Go/Hold/Pivot/Stopを透明に決める
この“お試し運転”の設計が、改善や持続可能なガバナンスと噛み合います。次の案件でも、まずはこの3週間の型から。必要に応じて現場への浸透支援(ロ-5)で並走し、「使われてナンボ」を一緒に作っていきましょう。
キミノマホロ for kintone
アールスリーでは業務改善・システム開発を行うサービスを「キミノマホロ for kintone」として提供しています。
「キミノマホロ for kintone」は業務改善のプロセスをイロハで3つのフェーズに分け、フェーズごとに作業をメニュー化しています。
【イ】業務改善の始まり:業務改善の方向性を決める
【ロ】業務改善に必要なkintoneアプリ作成:業務改善を実現するための仕組み(kintoneアプリ)を作る
【ハ】業務改善の実行サポート:業務改善を進める
今回の記事のようなお話は、ハのステップで弊社が気にしている内容になります。また、システム開発グループではkintoneに関するお悩み相談をお受けする「kintone駆け込み相談室」を随時開催しています。kintoneのシステム開発でお悩みの方がいらっしゃいましたらぜひお申し込みください!
投稿者プロフィール

- さすらいの、kintoneエンジニア