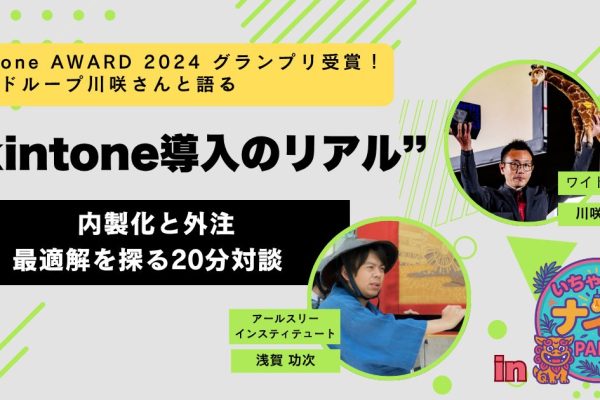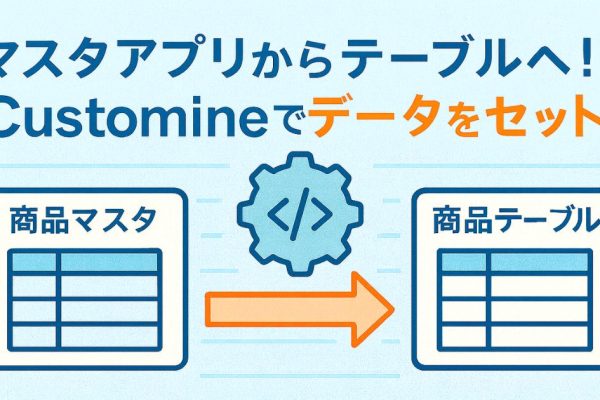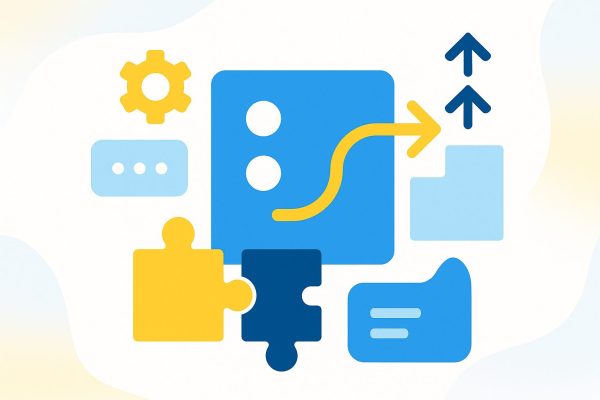公開日:
こんにちは!システム開発グループのかっつんです。
今日は物語を軸に、kintoneの良さ(+キミノマホロの良さ)をお伝えしたいと思い、書きました!
はじめに
「とりあえず、いっちゃんええのちょうだい」
(注:関西弁で「一番良いのください」)
家電量販店で、意外とよく耳にする言葉です。
けれど“一番良い”の意味が、”一番高機能”だとすると後々後悔するかもしれません。
この記事では、
自分で組み立てるパソコン = kintone
メーカー製のパソコン = パッケージシステム
というたとえ話を軸に、kintoneとアールスリーインスティテュートが提供するキミノマホロ for kintoneの魅力をお伝えできればと思います。
物語:二つの店、二つの選び方
「一番良いパソコン、あります!」
店員さんは胸を張り、最新CPU・大容量メモリ・多機能アプリてんこ盛りのメーカー製のPCを差し出します。
確かに高機能。けれど、重たい本体重量、学習コスト、そして気になる価格…。
さらに説明は続きます。「このモデルは動画編集も3DもOK。アプリケーションも初めから多く入っています!」。
頼もしさの裏で、お客様の頭の中には小さな不安が芽生えます。“ここまでの性能、本当に今いる?” “設定や慣れるのにどれくらい時間がかかるだろう”。
パソコン自体は悪くありません。むしろ、要件が合う場合には最強です。ただ、いま目の前の仕事に対しては、少しオーバースペックなのかもしれません。
次の店に入りました。
「ご用途は?」
お客様は答えます。
「んー、メールとネットが見れて、資料作成ができたら十分で、将来プリンタや外部モニタが増えるかも」
店員さんは頷き、ひとつ提案をしてくれました。
「自分でパソコンを組み立てるのはいかがでしょうか。」
「パーツを組み合わせことで、お客様でもパソコンを組み立てることはできると思いますよ。」
自分でパソコンを組み立てるのか。面白そう。だけど自分一人でできるのだろうか。
店員さんは私の不安を感じ取ってくれたのだろう。
「もしお客様自身で組み立てるのが不安でしたら、お客様がどのような使い方をされたいのかお聞かせいただけましたら、こちらで組み立ててお渡しすることもできますよ。」
そして、店員さんは私に丁寧にヒアリングをしてくれました。
将来的に、こんなことやあんなこともしたいという私の妄想にも嫌な顔せずに付き合ってくれました。
「お客様がストレスなく使える程度の機能で構成してみますね。将来的に使っていて不足している機能に気付いたときに拡張することも可能です。」
私は表情が少し緩みます。“必要な機能が手に入り、将来の道も閉ざさない”。
—
同じ「パソコン選び」でも、アプローチは対照的です。
前者は、機能が先にあり、人が合わせる。
後者は、人の使い方を起点に機能を合わせていく。
この違いは、総所有コストにも跳ね返ります。
大きな初期投資とトレーニングで一気に仕上げる方法は、条件が合えばスムーズ。
一方、小さく始めて学習と拡張を同じ速度で進める方法は、現場の負荷を均しながら確実に定着させます。
業務システムも同じだと考えます。
たとえば最初は「受付→対応→完了」の最短ルートだけを整備し、詰まりが見えた箇所にだけ承認や通知、外部連携を増設。
無駄なメニューや重たい画面を避けることで、ひとまず使ってみることができます。
- 前者は 機能 → 人に合わせる(全部入りで強力。要件が一致すれば最強)。
- 後者は 人 → 機能を合わせる(最小構成で出発し、必要に応じて育てる)。
どちらが“良い”ではなく、自社の仕事にどちらが合うか。この物語は、その見極め方を映し出しています。
例え話からわかる、kintoneの価値
- 最小で立ち上げ、早く使い始められる
まずは「受付→対応→完了」など、現場が動くための最短ルートから。 - 必要な機能だけを、必要なタイミングで増設
承認プロセス、通知、外部サービス連携などを運用しながら足す。 - 将来の拡張を見越した“拡張設計”
データの持ち方、権限の粒度、命名・連番ルールを最初に決め、やり直しを防ぐ仕組み作りは重要。
プラグインや連携サービスを組み合わせることでkintoneの基本機能だけでは実現できない機能を拡張できる。 - 学習コストと運用コストの平準化
使いながら覚える設計で、現場に定着しやすい。
アールスリーの進め方:キミノマホロ for kintone
最初に並べるのは「機能一覧」ではなく「現場の一日」
- 観察とヒアリング
誰が/いつ/何を/どの順番で業務を行っているのか。
Excelでの共有、紙ベースの作業手順、口頭の合図まで追っていきます。 - 現状の業務整理
コストをかけてでも解決したい悩み(ペインポイント)を明確にします。 - 「作るもの」「作らないもの」の決定
必要な機能を洗い出した後、機能の優先順位や費用対効果を考慮して、「作る」機能と「作らない」機能を整理します。 - kintoneを使った実現イメージ検討
画面が簡単に作れて変更もしやすいkintoneの強みを活かし、kintoneアプリを作りながら実現方法を考えます。
パッケージシステムと迷っている方へ
パッケージは初日から機能が揃って見える反面、
運用を合わせるための時間・教育コストが大きくなりがちです。
一方、kintoneは最小構成で素早く運用を開始し、必要な機能だけを追加できます。
“わかる”と“使える”のズレが少なく、現場のストレスを減らせます。
まとめ:「一番高機能」ではなく「最適」を一緒に
“ハイスペックなパソコン”は魅力的。
でも毎日の仕事に寄り添うのは、あなたの使い方に最もあった一台。
アールスリーインスティテュートのキミノマホロ for kintoneは、現場に馴染む仕組みをあなたと一緒に組み上げます。
まずは、現場の一日から。お気軽にご相談ください。
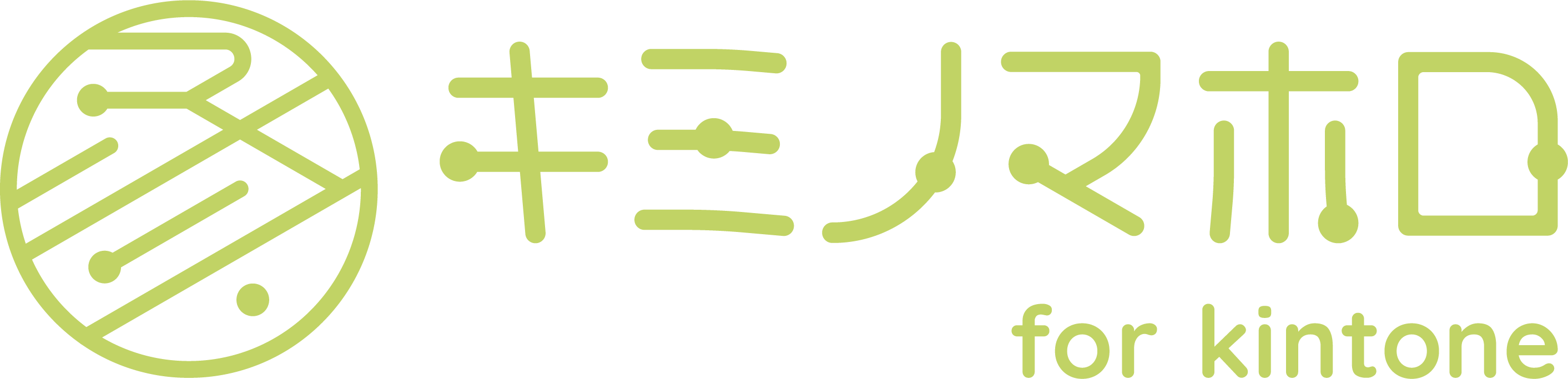
必要なものを、必要なだけ。
業務改善の新しいカタチ。
kintoneを活用した業務改善・システム開発サービス
kintoneを活用した業務改善・システム開発サービス
投稿者プロフィール

-
システム開発グループ所属。
滋賀県の琵琶湖近くに生息しています。
kintone CERTIFIED
┗ カイゼンマネジメントエキスパート
┗ システムデザインエキスパート
最新の投稿
 kintone2025年11月11日対談企画「kintone導入のリアル」 in いちゃりばないと 開催レポート
kintone2025年11月11日対談企画「kintone導入のリアル」 in いちゃりばないと 開催レポート gusuku2025年10月29日カスタマインを使って、マスタからテーブルに値をセットしよう!
gusuku2025年10月29日カスタマインを使って、マスタからテーブルに値をセットしよう! kintone2025年9月2日「一番良い」より「あなたに合う」——kintone×キミノマホロが選ばれる理由
kintone2025年9月2日「一番良い」より「あなたに合う」——kintone×キミノマホロが選ばれる理由 kintone2025年7月16日kintone「タスク管理アプリ」を“まず”作る理由
kintone2025年7月16日kintone「タスク管理アプリ」を“まず”作る理由