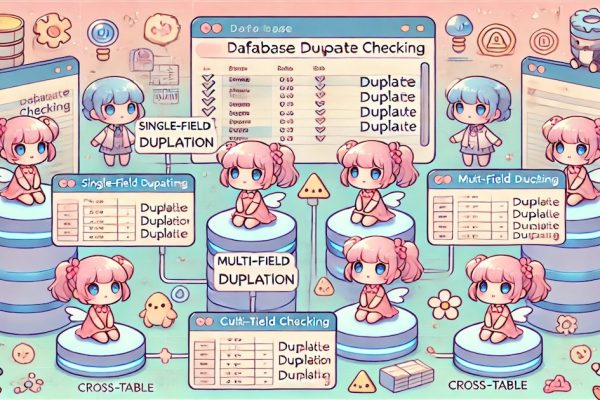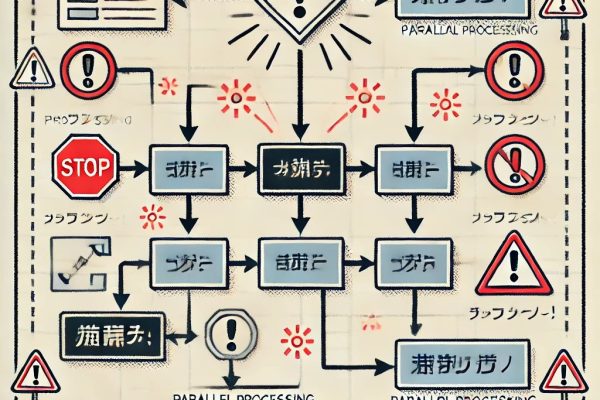公開日:
夏真っ盛りの沖縄からこんにちは、西島です。でも季節はちゃんと少しずつ流れているようで、最近日が昇る前まではちょっと朝が涼しくなって、犬の散歩が少し楽になってきました。
さて今回は、みんな大好き生成AIの活用事例をご紹介しようと思います。
すでに最先端の界隈では「使える?使えない?」という様子見の段階から「どのように統制を取りつつ活用するか、どう成果を測定するか」という段階に進んでいる状態ですが、なかなか一般的な企業ではまだまだ広く普及しているとは言い難いかと思います。
そんないわゆる普通の企業に所属する皆様に向けて、「こんな方法もあるよ」「ただこれは用意しておかないと駄目だよ」というような、最初の一歩となれるような事例をご紹介したいと思います。
よく「お問い合わせ対応に生成AIを活用して効率化!」のような謳い文句を目にするかと思いますが、実際のところどうなのか、という点からも参考にしていただければと思います。
カスタマインのサポートチームを支援する生成AIのボットについて
弊社のgusuku Customineではフリープランを含めすべてのお客様にチャットサポートを提供しています。このサポートチームを支援するための生成AIを使ったボットがありまして、2023年12月頃から構想を練りつつ構築し、翌2024年1月ごろから実際に稼働しています。
支援ボットなのでサポートチームのメンバーを支援し、お客様とは直接やり取りはしないというところがポイントです。これによって開発範囲を狭くして素早くリリースすることを目標としました。 機能的にはシンプルで、生成AIが活用されている部分としては以下のような機能を提供しています(生成AIと切り離された機能も実装されています)。
主な機能
- チャットの成り行きを観察して、問題がありそうであればツッコミを入れる
- 回答案の作成
- チャット終了後の分析と振り返り
こういった表向きの機能はもちろん大事なのですが、それ以前にもっと重要なのが、これらの機能を提供するために生成AIが利用できるデータソースをどうするかという問題があります。

生成AIのためのデータソースの重要性
会社の中にはいろいろな情報が散在していることと思いますが、それをどのような形で整理し、生成AIに読ませるか・活用させるかという点は、難しい点のひとつだと思います。技術的な点は弊社のような専門家に任せるとしても、考えるべきポイントは以下のとおりです。
これらの問いに答えられないようであれば、その情報を参照するのが人間でも生成AIでも、正しい答えを取り出せないので意味がありません。ですのでまずは、この観点から社内のデータソースを精査してください。
kintoneアプリをデータソースにする場合
kintoneを導入されている企業であれば、情報の集積場所は確保できているのでまずはひと安心です。 次は、そこに誰がどうやって情報を蓄積しているのかという観点から始めて、続いてその情報を活用するには?という流れで眺めてみると良いと思います。
例えば、問い合わせの履歴があるkintoneアプリで管理されているとします。この状況であれば次の質問は、以下のような点が考えられると思います。

- その問い合わせ管理アプリは、そもそも日常的にみんなが利用していますか
- 書き込まれてる内容は文字ですか、写真などの画像が多いですか、それとも音声ファイルなどですか
- 文字情報は、直接やり取りした文章そのままですか、それともその後精査した要約・概要がどこかにありますか
生成AIに渡す情報としては一次情報に近いほどよいケースもあれば、それをまとめて共有すべき知識に昇華しておかないといけないケースもあり一概には言えないのですが、最終的には改善したい課題にあったデータソースが用意できそうかという点がポイントとなります。
目的として、問い合わせの内容や傾向を分析したいのであれば一次情報がないとどうにもならないですし、ナレッジとして活用したいのであれば、そこから一旦共有知に変換する作業を人間もしくは生成AIにより行わなくてはいけません。
正直、個々の情報の粒度については、実際にやってみないと分からないケースも多いので、データが用意できたら一度RAGなどを組み合わせて生成AIに投げてみて、どのような動きになるのかを試すのも良いと思います。
「そう言うのは簡単ですが」というおはなし
上記のような情報の精査や更新の話はあちこちで見聞きすることと思いますが、実際に運用するのは非常に大変です。
弊社の場合には、現時点(2025年8月)ではおもに2つのデータソースを日々メンテナンスし、生成AIのデータソースとして利用しています。
サポートサイトやドキュメントサイトにはそれぞれ数百ページに上る記事とリファレンスマニュアルがありますが、これを日々メンテナンスしています。若干心が折れそうなくらい膨大な作業量になるのですが、もともとユーザー向けに一般公開している情報を生成AI「も」利用しているという点が少しだけ気休めになってくれます。
もし生成AI「だけが」利用するデータソースを新規に作ろうと考えているかたは、運用負荷やそのプロジェクトの継続性の観点から厳しく見つめ直したほうが良いかもしれません。
データソースの作成を社内的には「AIのご飯」と言っているのですが、美味しいご飯を食べさせてあげるほど、きっと良い結果が得られますので、ここは頑張るだけの価値はあります。逆に、データソースの品質が今ひとつだと、期待したほどの結果が得られない危険性も上がりますので、要注意です。 ぶっちゃけ すべてはここにかかっている と言っても言い過ぎではないです。
まとめ
さて、この支援ボットの効果のほどはといいますと、導入後にサポートチームのメンバーにヒアリングしたのですが、以下のような回答をもらいました。なお、コメントは修正していません!
現場の生の声(圧力なし)
- 文章が丁寧で良いですね
- チャットが解決に向かっていないときに、ちょっと待って、と冷静に突っ込んでくれるので、頭を切り替えるきっかけになります。今の方向性で頑張って、と応援してくれることもあって、ほっこりします。
- 内容によっては、ほぼそのまま回答できる回答案を出してくれることがあって助かる。そうでなくても少し直せば回答できるので、時短で回答できる点も助かります
- 類義語を教えてくれたりするので言葉の引き出しが増えました😁
色々と忙しすぎてリリースしてからあまり機能追加らしい追加が出来ていないのですが、使用するLLMだけはリリースされるたびに切り替えており、立ち上げ当初のAnthropic Claude 3 Sonnet から現在は Sonnet 4 を使用しています。LLMを切り替えるだけで基礎的な能力の向上を感じられるのは、ある意味ではホットな技術要素を活用するメリットのひとつかもしれません。
ただ、これから生成AIを活用した社内プロジェクトを立ち上げようと考えているかたに一言お伝えするとしますと、期待値コントロールは相当慎重に行ったほうが良いかと思います。メディアなどで宣伝された「生成AI万能説」と、自社の現状のギャップを理解しないまま行ってしまわないように気をつけましょう。
この記事が何らかの参考になり、皆様の業務改善が生成AIを活用することで効率よく進むことをお祈りしております!
投稿者プロフィール
-
"沖縄の自宅からリモートワークで参画している根っからのクラウド・コミュニティ大好き人間。
オープンソースとクラフトビールをこよなく愛する。"